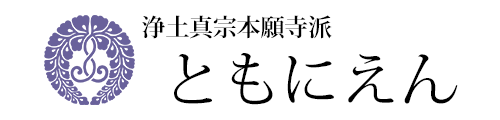親鸞聖人について

親鸞聖人-浄土真宗の祖
親鸞(しんらん、承安3年4月1日 - 弘長2年11月28日 [注釈 6])は、鎌倉時代前半から中期にかけての日本の僧。親鸞聖人と尊称され、鎌倉仏教の一つ、浄土真宗の宗祖とされています。法然を本師と仰いでから生涯に亘り、「法然によって明らかにされた浄土往生を説く真実の教えを継承し、さらに高めて行く事に力を注いだ。自らが開宗する意志は無かったと考えられています。
独自の寺院を持つ事はせず、各地に簡素な念仏道場を設けて教化する形をとる。その中で宗派としての教義の相違が明確となり、親鸞の没後に宗旨として確立される事になります。浄土真宗の立教開宗の年は、『顕浄土真実教行証文類』の草稿本が完成した1224年(元仁元年4月15日)とされるが、定められたのは親鸞の没後です。
六角夢告
建仁元年(1201年)の春頃、親鸞29歳の時に叡山と決別して下山し、後世の祈念の為に聖徳太子の建立とされる六角堂(京都市中京区)へ百日参籠を行いました。そして95日目の暁の夢中に、聖徳太子が示現され、
「行者宿報設女犯 我成玉女身被犯 一生之間能荘厳 臨終引導生極楽」
意訳 - 「修行者が前世の因縁によって[注釈 14]女性と一緒になるならば、私が女性となりましょう。そして清らかな生涯を全うし、命が終わるときは導いて極楽に生まれさせよう。」という偈句(「女犯偈」)に続けて、「此は是我が誓願なり 善信この誓願の旨趣を宣説して一切群生にきかしむべし」の告を得ます。この夢告に従い、夜明けとともに東山吉水(京都市東山区円山町)にある法然が住していた吉水草庵を訪ねます。(この時、法然は69歳。)
そして岡崎の地(左京区岡崎天王町)に草庵を結び、百日にわたり法然の元へ通い聴聞をします。法然の専修念仏の教えに触れ入門を決意します。これを機に法然より「綽空」(しゃっくう) の名を与えられる。親鸞は研鑽を積み、次第に法然に高く評価されるようになりました。


東国布教
時は流れ、1207年(建永二年、承元元年)後鳥羽上皇によって承元の法難により法然の門弟4人が死刑とされ、法然及び親鸞も流罪とされました。5年後の建暦元年(1211年)11月17日、岡崎中納言範光を通じて勅免の宣旨が順徳天皇より下ります。勅免後の親鸞についての動向には二つの説があります。一つは京に帰らず越後にとどまったとする説、もう一つは関東に赴いたとする説です。一方法然は、建暦2年(1212年)1月25日京都で80歳をもって入滅します。
その後、親鸞は建保2年(1214年)(流罪を赦免より3年後)、東国(関東)での布教活動のため、家族や性信などの門弟と共に越後を出発し、信濃国の善光寺から上野国佐貫庄を経て、常陸国に向かいます。
そして笠間郡稲田郷の領主である稲田頼重に招かれ、同所の吹雪谷という地に「稲田の草庵」を結び、この地を拠点に精力的な布教活動を行いました。また、親鸞の主著『教行信証』は、「稲田の草庵」において4年の歳月をかけ、元仁元年(1224年)に草稿本を撰述したと伝えられれいます。親鸞は、東国における布教活動を、これらの草庵を拠点に約20年間行いました。
浄土真宗本願寺派 ともにえん|大阪・関西 完結葬・葬儀のご相談はともにえんへ070-5262-8864受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ